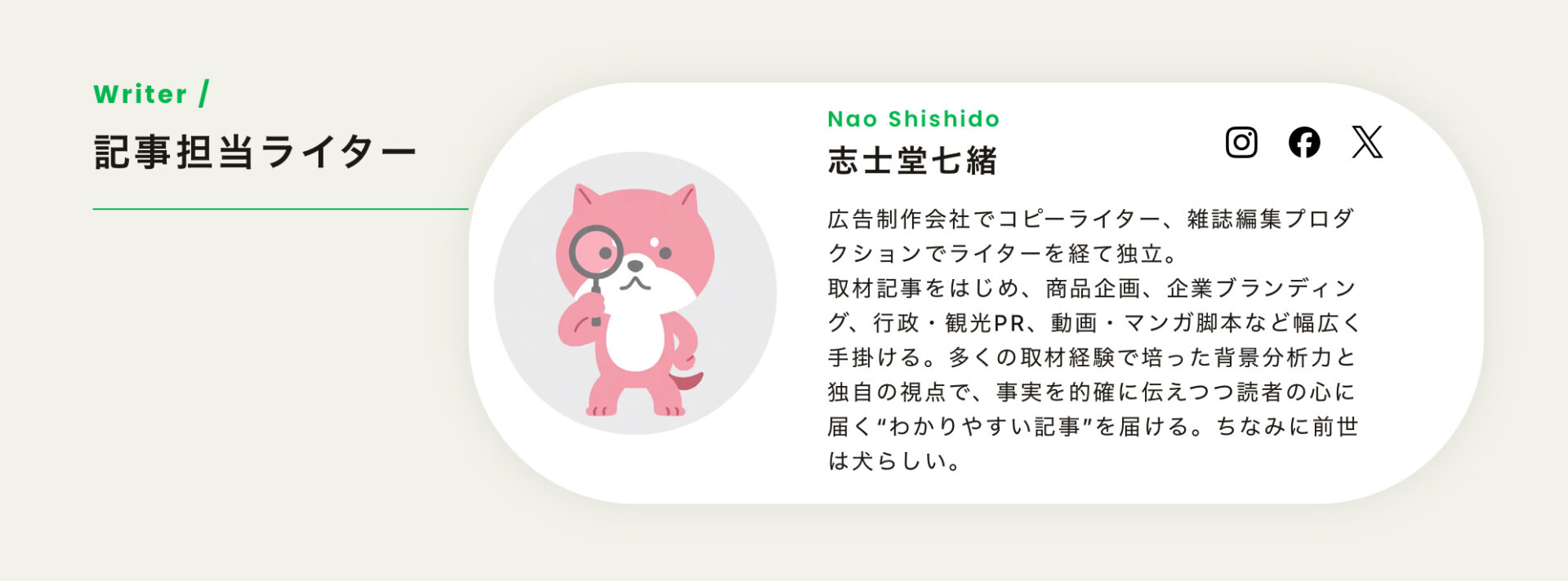Column
コラム
人気ライターの志士堂さんがPICKPRESSで記事にしてくれました!
https://preview.studio.site/live/VGOKGP07On/contents/00002
人気ライターの志士堂さんがPICKPRESSで記事にしてくれました。
目次
なわとびが学力に効く時代に──科学が証明する“跳ぶ習慣”の効能とは?

かつて子どもの遊びだった「なわとび」は、いま、
学力・認知能力・心身の発達を促す科学的ツールと認識されつつある。
単なるジャンプ運動ではなく、脳機能と身体能力を同時に刺激する運動として、研究成果とともに注目を集めている。
「なわとびをやったことがない人」いますか?
野球をやったことがない人はいても、なわとびを一度も跳んだことがないという人は、圧倒的に少数派だろう。
その理由は単純明快。なわとびは、日本の小学校で冬の体育の“定番種目”となっているからだ。
しかし、なわとびが広く普及しているのは、単に「手軽な運動だから」ではない。
なわとびは、運動機能だけでなく、
リズム感・協調性・集中力・自己調整力といった“非認知能力”をバランスよく育てられる、
極めて優れた教材だからだ。
そして今、教育や発達支援の現場では、その価値が再び注目を集めている。
なわとびが“究極の運動”と呼ばれる理由
なわとびは、運動科学で定義される「7つのコーディネーション能力」をすべて鍛えることができる、
非常にめずらしい全身運動である。
– リズム能力(テンポに合わせて跳ぶ)
– バランス能力(空中・着地で体勢を保つ)
– 反応能力(ロープの動きに合わせてタイミングよく跳ぶ)
– 変換能力(前跳び→後ろ跳びなど動作を切り替える)
– 連結能力(手の回転とジャンプを協応させる)
– 定位能力(ロープとの距離感を把握する)
– 識別能力(跳ぶ力加減やロープのスピードを調整)
通常の運動では、これらの能力のうち一部しか使われない。
たとえば、サッカーは反応・連結・定位、体操はバランス・変換・識別、
ランニングはリズム・持久力を主とした運動であるように。
だが、なわとびはこの7種類すべてを同時に鍛えることができる唯一の運動なのだ。
しかも、シンプルで、場所を取らず、個人でも集団でも取り組める。体力づくり、気分転換、ダイエット、
すべてにおいて「とにかく、なわとび」なのである。
子供たちの健やかな発達のために必要不可欠
そんな万能運動なわとびであるが、近年、感覚統合や神経科学の分野では、その潜在的な効果に注目が集まっている。
中国で行われた2024年の研究では、6~12歳のADHD児童を対象に8週間の縄跳び介入を実施したところ、
ワーキングメモリの正答率や心肺持久力が有意に改善され、
不注意や衝動コントロール能力にも改善傾向がみられたという結果が報告されている。
また、ハーバード大学の教育研究でも
「縄跳びなどのリズム運動が、記憶力・注意・制御機能を伸ばす習慣として有効」という報告があり、
発達支援の現場でも導入が進みつつある。
感覚統合が学力にも影響を与える
また、学力との相関性にも注目。中国で実施された3年縦断研究では、
「1分間の連続跳び記録」が高い児童ほど、その後の学業成績が伸びる傾向があったという結果がある
[出典:Frontiers in Public Health, 2023]。
つまり、なわとびは単なる体力づくりの道具ではなく、“学力や認知機能を支える身体活動”として機能している可能性があるのだ。
感覚運動発達の専門家である中京大学名誉教授・湯浅景元氏は、
「なわとびには、子どもの“運動発達”と“学習能力”を結びつける要素がすべて詰まっています」と話す。
「とくに3歳〜7歳の時期に、成功体験として“跳べた”を積み重ねることは、
その後の身体感覚、自己認識、学力形成にまで良い影響を与えます」。
“跳べた記憶”が、子どもを前に進ませる
ところであなたはどうだろう、なわとびは得意だっただろうか。
「嫌いだった」と答えた方は、「跳べなかった」のではなく、「跳べるように導かれなかった」だけかもしれない。
国内シェアNo.1なわとびメーカー・株式会社ベルテック鈴木啓子さんは
「幼い子だと回し方が不安定で、ロープがよじれた状態で足元にくるので、ひっかかりやすいんです。
本当は、道具が合っていなかったり、正しい跳び方を教わっていない場合が多いのですが、
跳べないのは自分のせいと考え、成功体験のないまま苦手と感じてしまう子が多いんです」と話す。
なわとび嫌いの裏にある“構造的なつまずき”を解消
ベルテックによれば、子どもたちがつまずく原因の多くは、
「道具が合っていない」
「跳べない子への指導がない」
ことに起因しているという。
はじめてのつまづきは、その後も尾を引く。
「最初の1回を成功させて、みんなに“スゴイね!”と褒められるなわとびを作りたい」
そんなコンセプトで誕生したのがベルテックが発売した『はじめてジャンプ』(販売中)だ。

「うまく跳べない=力がない・肩で回してしまう→ロープがよじれる」という現象に対して、
どんな回し方をしても、ロープがよじれず、まっすぐに足元にくるように、長さの違う3種類の「カバー」をつけている。
自転車なら、いわば補助輪みたいなもの。
うまく跳べるようになれば、カバーを外すこともできるという。
これは「できない子を切り捨てる」ものではなく、
「できる環境をつくる」ためのユニバーサルデザインということではないだろうか。
はじめての成功体験で、自信をつけ、もっと挑戦したい、という心を育てるのだ。
跳べる道具が、未来を変える
勉強ができる子は、最初から「賢かった」わけではない。
挑戦して「できた」記憶が、自分を信じる姿勢をつくっていった。
同じように、運動も「才能」ではなく、「体験の設計」から始まる。
跳べる子を増やすことは、伸びる子を増やすことと同義である。だから今、跳べるように作られた道具が必要なのだ。
『はじめてのなわとび』は、その最初のジャンプを応援する。
【株式会社ベルテック】
株式会社ベルテックは、昭和36年に創業。日本で初めてビニール製のなわとびを作ったメーカーで、らせん模様の塩ビなわとびは一世を風靡。NPO団体「日本なわとびプロジェクト」(JJRP)を設立し、跳び方の指導やイベント等の活動を定期的に行っている。