Column
コラム
“なわ”が違えば、跳び心地がまったく違う。
“なわ”が違えば、跳び心地がまったく違う。
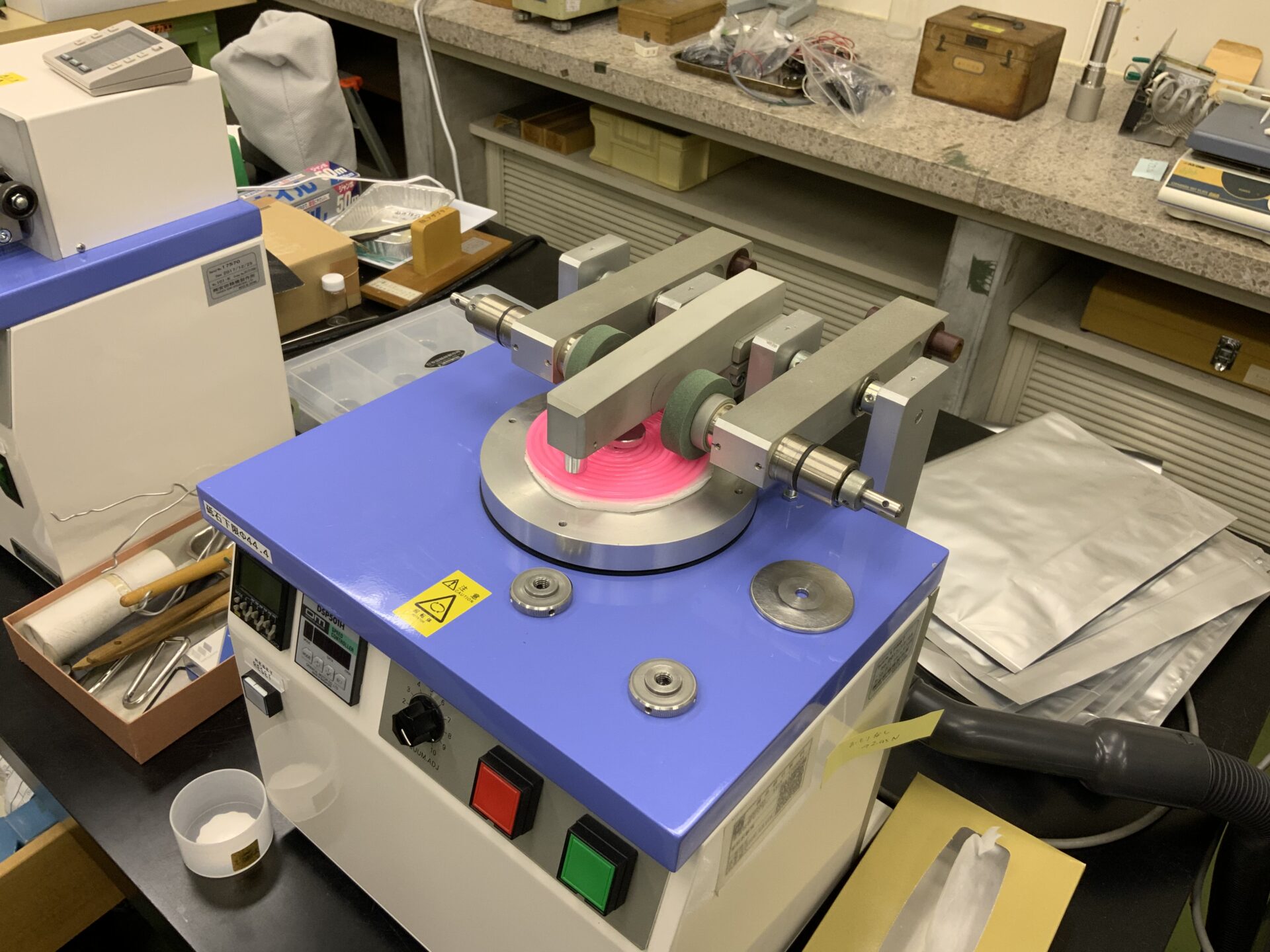
“なわ“が違えば、跳び心地がまったく違う。
私たちがなわとびの製造・開発に携わる中で、ずっと不思議に思っていたことがあります。
それは、「市場に出回っているなわとびを実際に跳んでみると、跳び心地がまったく違う」ということです。
なわとびという製品は、一見すると非常にシンプルな構造をしています。グリップ(持ち手)があり、そこからロープ(なわ)が伸びている。ただそれだけ。ところが、実際に手に取って、跳んでみると……違うのです。しかも、その違いは見た目やスペックではほとんど判断がつきません。
私たちはまず、その違いの正体を突き止めるために、様々ななわとびを分析しました。
グリップの長さや太さ、手に持ったときの重さ。グリップとロープをつなぐ回転部分の構造や滑らかさ。これらも確かに影響はありますが、何十種類と試していく中で、最も違いを生む要素が見えてきました。
それは「なわ(ロープ)そのもの」です。
感覚はある。でも、言語化されていない。
同じような素材のなわとびでも、ロープを変えるだけで跳び心地が激変します。
「このなわ、なんか軽くて跳びにくい」
「これはスピード出るけど、ミスしやすい」
「ちょっと重いけど、タイミング取りやすい」
こうした感覚的なコメントは、子どもから大人まで多くの人が共通して感じていることです。
しかし不思議なことに、店頭に並んでいるなわとびのパッケージを見ても、
「このなわはこういう特性があります」と書かれているものは、存在しません。
「材質:PVC」「長さ:2.5m」といった最低限の表記こそあるものの、そのなわがどんな跳び心地を持っているか、あるいはどういうレベルや目的に適しているかといった情報は、まるでブラックボックスのように曖昧なままです。
つまり、私たちが感じている“跳び心地”は存在しているにもかかわらず、
それは言語化も数値化もされていない、完全に無意識の領域にある情報だということです。
跳びやすい・跳びにくいは、「選ばれて」いる
とはいえ、子どもたちがなわとびを選ぶとき、何も考えていないわけではありません。
「これなら跳べる気がする」「なんか跳びにくい」「やっぱり前のやつのほうが好き」
無意識の中で、彼らは“選んでいる”のです。使い慣れたなわとびの感覚と、手にした新しいなわとびとの微妙な違いを、言葉にはできなくても身体が記憶している。そして、跳んでみて、身体が教えてくれる。「これじゃない」「これだ」と。
この現象を、私たちは重要なヒントだと捉えました。
跳びやすい・跳びにくいには確実に物理的な要因があるはずなのに、それが説明されていない。
つまり、私たちがやるべきことは、この無意識の感覚を「意識化」し、「数値化」することだと確信したのです。
「感覚」と「数値」のあいだに橋をかける
跳び心地という、これまで感覚に委ねられていた世界に、どのようにして数値的な裏付けを与えることができるか。
そしてその数値は、実際の跳びやすさとどうつながるのか。
私たちはこのテーマに真正面から取り組むことにしました。
そして次章では、その数値化に向けて私たちが行った世界初の試み——
あいち産業科学技術センターとの共同研究、
そして“跳び心地”という曖昧な感覚を測定するために生まれた装置「測定くん」について紹介していきます。






